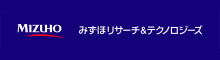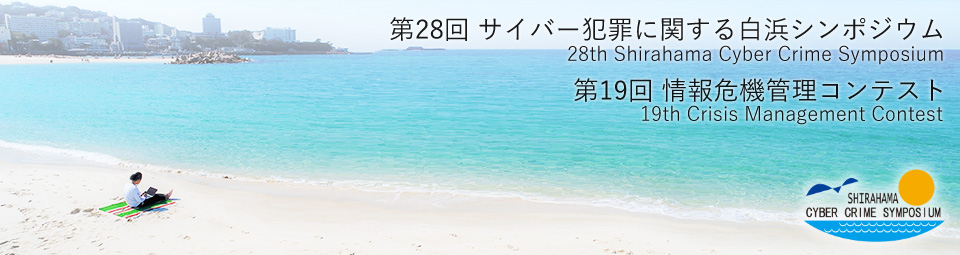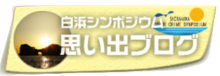講演内容

今回も、この1年を振り返って、国会で成立したサイバー関連立法、関連指針などについて、できるだけ分かりやすく解説する予定である。
それに加え、インターネット等を利用した選挙運動(ネット選挙運動)が、大きな注目を浴びた年でもあった。これは約10年前の公職選挙法改正によって“解禁”されたものであるが、“解禁”の経緯・内容を簡潔に整理した上、この1年の間に、その“光”と“影”の部分として、どのような点が新たに問題となったのかについて、国際的な動向も踏まえつつ、できる限り新しい検討状況について解説を加えたい。

デジタル社会という単語が明確な定義もない中でも普遍的に使われるようになった昨今、その「社会」で「暮らす」人々のアイデンティティというのは一体どういうものでしょうか。そもそも単語だけは良く聞く「アイデンティティ」ですが、『デジタルアイデンティティ』とはどういうもので、更には、プライバシー、そしてセキュリティとはどういう関係にあるのか。単なる「アカウント」とアイデンティティの違いはどこにあり、今後の我々にどういう影響と意義があるのかをご紹介したいと思います。

深層学習技術の発展に伴い、「画像生成AI」と呼ばれる技術も目覚ましい発展を遂げています。ここ10年程の間に、いくつものブレークスルーとなる重要な技術が生まれ、一見しただけではリアルなカメラ写真と見分けることが難しい画像を生成できるようになりました。しかも、誰でも簡便に生成することができる環境も構築されています。そのため、技術の悪用も懸念されています。
本講演では、現在の画像生成AI技術でどのようなことが行えるのか、どういう原理で画像を生成しているのか、その特徴などについて述べます。また、リアルなカメラ写真なのか、生成したフェイク画像なのか判別するための技術についても概観するほか、現在我々が行っている研究の内容なども紹介します。

情報通信技術の発展が社会に便益をもたらす反面、インターネット空間を悪用した犯罪が脅威となっている。例えば、インターネットバンキングに係る不正送金事案や、SNSを通じて金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺、暗号資産を利用したマネー・ローンダリングが発生するなど、インターネット上の技術・サービスが犯罪インフラとして悪用されている実態がみられる。
このような状況に対し、警察においては、国際共同捜査の推進、暗号資産の追跡など検挙に向けた取組を進めるとともに、被害の未然防止・拡大防止に向けた様々な取組を実施している。
本講演では、最近のサイバー空間における脅威情勢と、警察の取組について、紹介する。

子どもたちのネット活用が広がる一方、様々なネットトラブルの被害を受けるだけでなく、サイバー犯罪の加害者になってしまうリスクも増加しています
本講演では、若年層のネット活用における各種データを踏まえ、家庭や学校が行う教育的サポートだけでなく、企業や警察、社会全体で取り組むべき課題についてお話しします

サイバー犯罪の捜査は、多くがデジタル記録の追跡です。過程では数多く照会を発出し、電磁的記録を差押えます。その照会に回答する、差押えに応接する民間人は、どの様な職位で、どの様な仕事を、普段はしているのでしょうか。
民間側担当者の働き方を知ることは、捜査の円滑化に資します。
その担当者は案外、事業者の中で犯罪対策も担っていたり…、さらに通信の場合ともなると、オンラインハラスメントのレビューもしていたり、訴訟の事務、テイクダウン、インシデントレスポンスまで担当していたり、します。
もし所属する組織でクラウド・インシデントが起こったら? 身近な人がオンラインハラスメントを受けたら? どのように窓口の担当者とコミュニケーションしたらいい?
あるいは担当することになった場合、どのようなキャリア戦略を描けば人材価値を維持できるでしょうか。会社が潰れた、身上の都合が生じた、…どうしましょう?

システムが複雑に絡み合ってサービスを提供する、今やどこの組織でも見られる当たり前の光景である。もちろん組織の成り立ちに依ることがほとんどであるが、およそ時間的経過ないし組織経緯に応じて認証機能が乱立し、もはや組織全体におけるIDの把握すら困難になりつつある現場に違和感をもしかしたら感じたことがあるかもしれない、その意識を与えた要因の1つがコロナ禍である。世界中が否応なしに巻き込まれ世の中は一気にMS365導入などクラウド化が進んだことは記憶に新しい。結果として、複雑怪奇な認証の複雑さを何とかしようという流れを見せつけてきたのである。長年の間にIDとパスワードの世界がセキュリティの根幹であるということを刷り込まれ続けてきたのだが、この数年でパスワードレス認証などをはじめ、一気にIDからの脱却に進み始めた。
本講演では、IDではなく個々人のアイデンティティに着目し、講演者が構想してきた大学におけるアイデンティティの取り組みについて紹介するとともに、2025大阪・関西万博での事例などを踏まえ、10年後の2035年を見据えた認証のあり方について言及してみたい。

調整中

3日目 13:00-14:20 (パネルディスカッション)
調整中
調整中
BOF (1日目 20:00-21:40)

DX推進の昨今色々なものがオンライン化されています。例えば企業間の請求書をはじめとした書類の送受信、商品の受発注業務などもオンライン化されています。それらのオンラインシステムを利用するためには必ずIDとパスワードで本人確認が必要です。ですが、取引先のオンラインシステムに登録されたIDは誰が管理するのでしょうか?社員が外部のシステムへ登録したIDは、社員が辞めた後にも残り続けますが、誰がどうやって消去したらいいのでしょうか?
中小企業の現場ではセキュリティ専門家が想像する以上のスピードで管理されないIDが増えています。このBoFではその現実の共有と解決を中心にディスカッションしていきます。

厚生労働省の閉鎖済みコロナ窓口サイトが FX 勧誘ページに、国土交通省の旧サイトがオンラインカジノ広告に――こうした報道が相次いでいます。
共通する原因は、本格利用を終えたドメイン名の管理が甘かったこと。
本BoFでは、放置ドメイン名が悪用される手口と、請負構造が抱える課題を解説したのち、「ドメイン名をどう活用・終活するか」「不正利用をいかに防ぐか」をディスカッションします。

Attack Surface Management(ASM)製品は、費用対効果の高いセキュリティソリューションとして普及が進みつつありますが、当然のように他のセキュリティと同様、奥の深い領域を持ちます。
導入や価格がライトウェイトな製品も目に付く中で、冷静にASM界隈のライトサイドと、強力さ故一歩間違うとある意味でのダークサイドに落ちるだけの側面があり、ASMのもたらしたセキュリティ観点の社会変容についてその専門性と倫理感等を踏まえた議論できればと思います。
・組織をスコアリングするというのはどういうことなのか?
・「外形的にわかる」ということの意味
・何を見るのか
・「他者」をも数値化できるということはどういうことか
・SCMと数値化の先にあるもの

教育と人材育成はその意味合いが若干異なる。
混ぜこぜになりやすいこのテーマは、全体像なき各論に陥りがちである。
また、時代の変化に合わせて取り組み自体も変化する必要もある。
そこで本BoFでは全体像を押さえながらいくつかの視点で論点整理しそれぞれ必要な教育と人材育成について取り上げる。
昔ながらのBoF(小グループごとのチャタムハウスルールディスカッションが中心)スタイルで、いま必要な取り組み自体の変化について参加者全員で議論する。

2025年度末,自治体システム標準化のタイムリミットが迫る中,ガバメントクラウドをめぐる問題が各地で噴出している.「本当にこれで地方自治は守れるのか?」「住民サービスは向上するのか?」そんな不安と疑問を抱える自治体職員,IT関係者,そして未来を憂うすべての皆さまへ.
・地方自治のアイデンティティは守れるのか?
・公共SaaSは中小自治体を救うのか?
・市民へのサービスはどのようにかわっていくのか?
・自治体はこの難局を乗り切ることができるのか?
・自治体がこの先生きのこるためには!